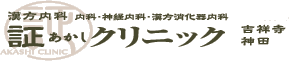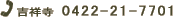膠原病とはどんな病気ですか
免疫とは、ウイルスや細菌などが身体に侵入した場合、これらを攻撃し身体を防衛する機能のことです。しかし、免疫が様々な原因(遺伝やウイルスの感染など)でシステムエラーを起こすと、免疫は自分の身体のさまざまなパーツに対しても攻撃するようになります。こういう病気を自己免疫疾患といいます。

自己免疫疾患では全身のあらゆる器官が攻撃対象となり、病気を起こします。一部の糖尿病は膵臓が、バセドウ病は甲状腺が、それぞれ自己免疫の攻撃対象となった病気です。自己免疫疾患の中で皮膚、関節、血管などに炎症が起こるものを膠原病と総称します。膠原病は、英語でcollagen diseasesというように、コラーゲンの関係する皮膚・関節・血管などに異常がみられます。膠原病には次のようなものがあります。
- 関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス(SLE)
- 皮膚筋炎(多発性筋炎)
- 全身性硬化症(強皮症)
- シェーグレン症候群
- サルコイドーシスetc.
どんな症状があれば膠原病が疑わしいのですか
膠原病は、皮膚、関節、血管などに炎症が見られるので、これらの器官に症状が出やすいのです。代表的なものをあげてみます。
皮膚の異常
目の回りや、手足の関節附近に多くみられます。赤くて大きな湿疹のようなもので、日光過敏症(紫外線皮膚炎)やアトピー性皮膚炎と誤診される例もあるようです。
関節の異常
手指、膝や肘などの関節のこわばり、腫れ、痛みがあります。熱を持っていることが多いようです。
血管炎
血管は全身にありますので、全身に異常が出る可能性があります。発熱、倦怠感(だるさ)のほか、上記の皮膚や関節症状も起こりえます。とくに心臓・腎臓・肝臓・肺・脳などの臓器に起こった血管炎の結果、血栓(血管内で血が固まる)を生じ、脳梗塞や心筋梗塞を起こしたり、その場所から出血することもあります。血管炎は命に関わるものも多く、緊急の処置を要します。
どんな検査で膠原病がわかりますか
膠原病は以下のような検査で診断することになります。
血液検査・尿検査
先ほど述べたように、膠原病は自己免疫疾患ですから、自己免疫をもっているかどうかが決め手になります。血液中の自己抗体と呼ばれるものをチェックします。炎症の強さ、種類を診るために、他の項目も同時に調べます。また、腎臓が血管炎を起こすと、尿に異常が現れますので、尿検査を実施します(いずれも当院で実施可能です)。
心電図検査
心臓に血管炎が起こっていないかどうかをチェックします(当院で実施可能です)。
レントゲン検査
関節の炎症や血管炎は外から観察できませんので、レントゲンやCTなどで身体の内部を診ることになります(これは当院では実施できません)。
実際には、どれかひとつの検査で診断できることはまずありません。複数の検査を組み合わせて、診断にたどり着きます。また、経過を追うのもこれらの検査を適宜組み合わせて行います。
検査の話ばかりしてきましたが、膠原病の診断では問診もとくに重要です。とくに、何週間も続く熱(37度程度の微熱も含む)、だるさ(全身または手足の倦怠感)は医師が膠原病を疑う最も基本的な情報です。熱・だるさが続いている方は、一度は膠原病を疑って診察をお受けになるほうがよいでしょう。
検査の結果、治療が必要と言われましたが、どんな治療をするのですか
膠原病は自己免疫疾患ですから、免疫を抑える治療を主体にします。また、膠原病は炎症の面もありますので、炎症を抑える治療も行います。ステロイドをはじめとしてさまざまな免疫抑制剤、抗炎症剤などの内服薬が用いられます。また、これらの薬には副作用が強いものが多く、副作用を軽減するための薬(胃腸薬、骨粗鬆症治療薬など)も一緒に用いられることがあります。最近では、治療効果を強め、副作用を減らす目的で、各種の注射薬も用いられています。いずれも、膠原病専門医のもとで治療を受けることが望ましいと考えます。
漢方では何ができるのですか
漢方薬には免疫を調整する作用があります。これを活かして、自己免疫疾患である膠原病を根本から治療できる可能性があります。
また、漢方薬の中には炎症を抑えるものもあります。一般の抗炎症剤ほど強い作用は期待できませんが、一般の薬では副作用が出て飲めない方のために、あるいは一般の薬の使用量を減らす目的で、漢方薬が用いられます。
いずれにせよ、現代医学的な検査・治療を専門医の元で行いつつ、そこに可能な漢方治療を併用していくのが最も安全・確実な方法でしょう。
そのほかの注意点
膠原病はいわゆる不摂生をすると発症しやすくなります。また、不摂生は膠原病を悪化させる要因でもあります。具体的には、食事や就寝時刻が不規則な生活、睡眠不足、疲れやストレスをためる、心配事が多い、食事を抜く、食べ過ぎ・偏食などは改善する必要があります。難しいと思いますが、ご自分に出来る対策なのです。また、皮膚症状がある方は、紫外線よけを厳重にすることが肝腎です。
当サイトが提供する情報等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます。
Copyright cAkashiClinic. All Right Reserved.