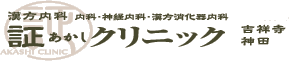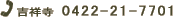漢方薬について

「漢方薬」は紀元前後の頃に中国で生まれた伝承医学における薬物療法で、さまざまな天然の植物・鉱物・動物由来の生薬を配合して構成されています。漢方薬の運用は、東洋医学的な診断方法(四診(望診・問診・聞診・切診))や理論(陰陽虚実・気血水論・五臓論)により、患者さん一人ひとりの体質に合ったお薬を選びます。
独自の理論や診たてによって、いくつかの生薬の配合による「処方」が決定されるという点で、「胃痙攣にセンブリ」・「下痢にゲンノショウコ」など、経験的に地域に伝わった“この症状なら誰にでも”という民間療法とは異なります。
「西洋薬」は化学的に合成されて臨床試験で効果が確認されたもので、一般に「新薬」とも呼ばれます。“アスピリン”や“ジギタリス”など、生薬・ハーブの成分が由来のものもありますが、新薬はほとんどが単一の成分のみで成り立っています。病態が明らかな場合や、診断がついて病名が決定された際に、一定の効果が保証さている点が優れています。しかしながら、新薬のみでは対応できない症状(特に体質的なものとされる虚弱や冷え、自律神経症状など)も数多く存在することが問題です。
これに対して漢方薬は、東洋医学的な病態把握によって、さまざまな成分を有する生薬を組み合わせることで、多彩な症状や複雑な病態に対応することが可能となります。また複数の生薬を配合することにより、有用な作用を相互に補い高め合ったり、胃腸障害などの副作用を軽減させたりする工夫が施されています。しかしながら漢方薬では、未だ薬理学的に作用が明確でないものが多く、その組み合わせや配合比の違いによる効果の差などについて、科学的にすべてを明らかにすることが大変困難なことが問題です。

もちろん漢方薬・生薬については、現在も科学の目による新たな評価・分析が進んでいますが、すべてが解明される日はまだまだ先のことでしょう。 現時点では、漢方薬が治療の中心となることもあれば、西洋薬であっさりと解決できることもあり、それぞれの適応の見極めとバランス感覚が大切かと思います。 現代医学的の優れている点をしっかりと認識して治療の機会を失うことなく、それでも対応困難な症状や病状には、漢方薬がお役に立てるものと考えています。
煎じ薬は、生薬を煮てカスを去り、ハーブティーあるいはスープの煮汁を取るようにして作ります。
エキス剤は、製薬会社によって生薬を煎じて抽出したものを加工して作られ、患者さんの煎じる手間を省き、携帯しやすいように工夫されています。エキス剤の品質は各企業の努力によって保証され、安定した作用が得られます。飲みやすいように、錠剤やカプセル剤も作られています。
このように大変便利なエキス剤ですが、製剤化されている処方の種類に限りがあることや、企業によっては同じ処方でも生薬の配合に若干の違いがあることがある点や、添加物の違いがあることなどに注意が必要です。
一方、煎じ薬では選択できる処方の幅が広がることや、処方中の生薬を必要に応じて加減ができるなど、一人ひとりに合うように調合できることが利点です。また漢方薬が持つ本来の味や香りも大切に出来ることも重要です。しかしながら逆に飲みにくいと感じることもあり、煎じる手間も若干かかります。
エキス剤
- 携帯に便利。手間がかからない。
- 処方の種類に限りがある。
- 既製品なので生薬の加減ができない。
- 飲みやすいようにオブラートに包むことが可能。錠剤やカプセル剤もある。
- その他 製薬会社によって、同じ処方でも生薬の構成や、添加物に違いがある。
煎じ薬
- 毎日、煎じる手間がかかる。
- 生薬の組み合わせに限りなし。
- 生薬の加減ができる。
- 漢方薬本来の香りや味が出せる。
- その他 一人ひとりに合うように調合し、より効果を高めることができる。

例えれば“コーヒー”のお話で、“煎じ薬”は“挽いた豆をドリップしていれたコーヒー”、“エキス剤”は“インスタントコーヒー”に似ています。 インスタントコーヒーは簡便ですが、すべての銘柄の豆やブレンドが手に入るわけではありません。ドリップして手間をかければ、味や香りといった深みが豊かになり、豆の配合もその方の好みに応じたものに作ることができるのです。
煎じ薬:煎じ方と飲み方
①1袋(1日分)を土瓶に入れます。
*生薬の成分と反応を起こす、ステンレスや鉄瓶は避けてください。
② 水をコップ(200cc)に3杯程度(薬500-600cc)入れます。
③ とろ火にかけて30分程煎じます。
沸騰するまでは強火で、あとは弱火でゆっくり。
フタは外して、煮詰めます。
“附子”・“烏頭”の入った処方の場合は、50分から60分程度と長めに煎じます。
下剤としての“大黄”の作用を強くする場合には、煎じ終わる直前に加えます。
*煎じる時間や生薬の加減については、医師または薬剤師にご確認ください。
④ 薬を半分ほどになるまで煎じ詰めます。
コップ1杯半ほどで、煎じ薬のできあがり。
⑤ 火からおろして、すぐにカスをこします。
“膠飴(アメ)”などの入った処方の場合は、カスを去ったあと温めながら溶かしてください。
⑥ 煎じ薬を3等分して、一日3回 食間(空腹時)にコップ半分(1回100cc)ずつ温めて飲んでください。
*専用の煎じ器を使用する場合は、電気式でタイマーをセットすることで簡便に煎じることもできます。 煎じ器は、インターネットでも購入できます。専門の薬局にも、お問い合わせください。
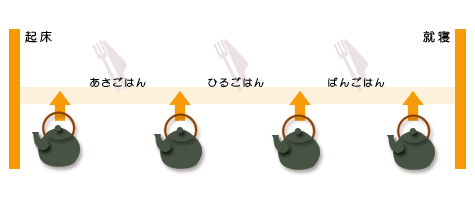
エキス剤の飲み方のコツ
コップ1杯のお湯に溶かして、空腹時に服用しましょう。
ポイント①
粉薬も煎じ薬のように、コップ1杯の湯に溶かして飲んでください。有効成分が吸収されやすくなります。また香りや味、温度も薬の大切な要素です。溶け残った成分も、飲んでしまいましょう。湯が用意できない場合には、溶かさずにコップ1杯の水で飲んでもかまいません。味・匂いが気になるときは、オブラートに包んでもよいでしょう。
錠剤やカプセルは、溶かす必要はありません。
なお吐き気のあるときには、冷水を使うと飲みやすくなります。“五苓散”には、冷服という服用法もあります。
*どうしても飲みにくい場合には、医師・薬剤師にご相談ください。
*幼児・小児に服用させる場合には、少量の水で練ってゼリーで包むのもよいでしょう。
ポイント②
空腹時とは食事の30分以上前、または食後2-3時間ほどが目安です。
食物の影響を受けにくいこと、速やかに腸内に運ばれることなどの理由から空腹時がよいのです。
ただし胃がもたれて食欲が低下したり、味や香りのために空腹時に飲みにくいことがあれば、食後に服用するのも一方です。医師・薬剤師にご相談ください。

漢方薬には、毒性の高いものは淘汰され副作用の少ないものが残り伝えられてきたという歴史的背景があり、その高い安全性には定評があります。しかしながら比較的軽度のものから、ごく稀に重度の副作用の報告もあるので注意が必要です。
風邪などでよく用いられる生薬“麻黄”を含有する処方で、胃もたれ、食欲不振、排尿障害、不眠、動悸が起きる可能性が知られています。
生薬“甘草”は多くの処方に含まれますが、この薬理作用のために体内のミネラル(ナトリウムやカリウム)のバランスに影響し、まれに浮腫や高血圧、筋力低下などを生じることがあります。
ごく稀に報告される重篤なものとして、「間質性肺炎」や「アレルギー反応」、「肝機能障害」があります。日常生活動作での息切れや呼吸困難、皮膚粘膜を含む痒みや湿疹、強い倦怠感や食欲不振、白色便・褐色尿が見られた場合には、すぐに服薬を中止し医療機関を受診して下さい。
こうした有害事象に対応するためには、専門医による適切な診たてが必要であるとともに、定期的な診察や血液検査を受けることが望ましいでしょう。 好ましくない身体の反応や症状に気付いたら服用を一時中止し、遠慮なく早めに医師・薬剤師に相談してください。

漢方薬の成分と新薬との併用についての影響は、まだ全てが明らかになっているわけではありません。 可能性として漢方薬の成分が肝臓で代謝を受ける際に、新薬の代謝を阻害してその作用を増強させることも考えられます。特に多くの診療科で投薬を受けている場合には、漢方薬・新薬を問わず、念のため医師に報告し相談するようにして下さい。
病気の程度や原因によっては、長期にわたる服薬が必要となることもありますが、急性に生じた症状については、即効性の期待できるものもあります。
また、漢方薬の代謝には腸内細菌の影響も受けます。長期に服用し続けることで、漢方薬の有効成分を代謝できる環境を整え作用が安定する可能性も知られています。根気よく服用することが必要となることもあります。

慢性疾患では概ね1-2週間程の服用で身体の反応を見て、処方の継続か追加・変更を検討しています。さらに長期に亘っては、体質の変化に応じて処方が変更されますので、定期的な診察が必要です。
生活習慣などの養生が見直され、治療によって心身の状態が改善された際には、投薬の廃止も可能となりますが、ストレスや病因の解除ができない場合には治療の継続が必要なこともあります。
* 漢方薬の効果が得られる前に、一時的に病状の悪化したような反応が見られることもあります。これを“めん眩”と呼びますが、この場合は服用を継続できるだけの “良い反応”を伴っていたり、“耐えられる程度”であることが多いようです。服用を継続してよいか判断に迷う場合には、医師・薬剤師にご相談ください。
生薬・エキス剤の保存はともに、高温や直射日光・多湿を避けて冷暗所で管理してください。
漢方薬は、一人ひとりの体質に合った処方が選ばれています。例え症状が同じでも、他の人に譲ったりするのは止めましょう。